スポーツによる痛み

目次 contents
腰椎分離症
腰椎分離症とは
小学校高学年、中学生くらいのスポーツを積極的に行っており、体が硬いお子さんに発症する腰椎の疲労骨折の一種です。
野球、バスケ、サッカー、陸上、水泳など様々な競技で起こりえます。
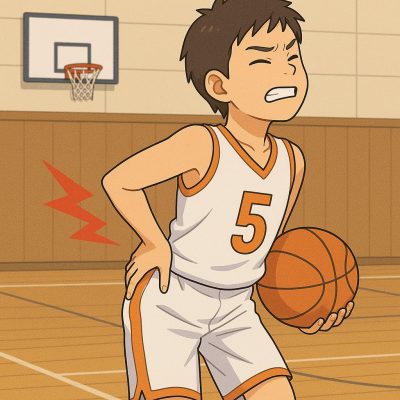
腰椎分離症の症状
運動時の腰痛が多いです。
症状が進行すると授業中などに座っていても腰痛が出現するようになります。
腰を後ろに反らしたとき、ひねったときに痛みが増強するのが特徴です。
腰椎分離症の原因
体が硬いことが原因となります。
体を反る動作をするときには、胸椎、ハムストリングスなども使用して体の反りを出しますが、体が硬いために胸椎や下半身がうまく使えず腰だけで反り動作を出してしまいます。
その状態で、スポーツの反復動作を行うと、腰椎の「椎弓」という左右にある生理的に弱い部分に負担がかかり骨折を起こしてしまいます。
腰椎分離症の診断
スポーツを積極的にやっている体が硬い小中学生が腰痛で受診された際は疑います。
まずレントゲン撮影を行いますが、レントゲンで判別できることはまずありません。
MRIやCTを行って確定します。
腰椎分離症の治療
腰椎分離症にはどの程度進行しているかを示す病期分類があります。
軽い方から、①初期、②進行期、③終末期があります。
①初期と②進行期分離症であった場合は、硬性コルセットという装具を着用して運動中止となります。
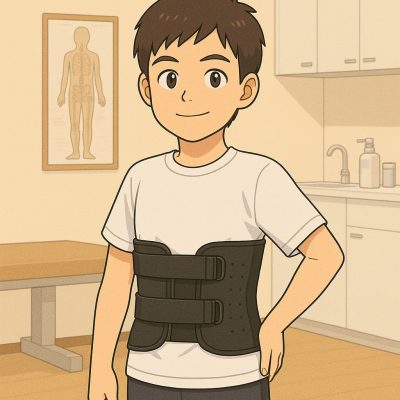
運動中止の間は、再発・腰痛予防のためにストレッチングやコルセットを装着しても体幹筋力トレーニングなどのリハビリに取り組んでいただきます。
運動中止の期間は、①初期分離症で3ヶ月半、②進行期分離症で6~9ヶ月と言われております。
③終末期分離症では、骨がくっつく(骨癒合)ことはないため、主にリハビリで腰痛予防を行います。
筋筋膜性腰痛症
筋筋膜性腰痛症とは
主に中学生くらいの成長期のお子さんの腰痛で、画像上はっきりした異常がなく、背骨を支える筋肉に痛みや硬さがある場合、筋筋膜性腰痛症を考えます。
筋筋膜性腰痛症の症状
運動時の腰痛のみならず、安静時の腰痛も訴えることもあります。
筋筋膜性腰痛症の原因
多くは体の硬さが原因となることが多いです。
筋筋膜性腰痛症の診断
背骨を支える筋肉(脊柱起立筋)付近の疼痛や触診で筋肉の硬さがあったり、脊柱起立筋の骨盤付着部の疼痛がある場合は疑います。
レントゲンやMRIで腰痛の原因になりそうな異常を認めないことが必要です。
筋筋膜性腰痛症の治療
思春期の筋膜性腰痛性は体の硬さが原因となることが多いため、ストレッチングをメインにリハビリを行っていただきます。
また、拡散型圧力波が有効であることもあります。
拡散型圧力波とは、痛みのある部位に衝撃波を照射することで、痛みをとり、組織を修復する治療です。
当院では、拡散型圧力波をリハビリの一環として取り入れております。
膝の前十字靱帯断裂
前十字靱帯断裂とは
膝の内部にある安定性を確保するのに大切な組織である前十字靱帯が断裂し、症状を来す疾患です。

前十字靱帯断裂の症状
受傷した直後から、膝の痛み、腫れが強くなります。
膝のぐらつき感を自覚する場合もあります。
前十字靱帯断裂の原因
特に中学生、高校生くらいの女性に多いです。
そのくらいの年代の女性が、バスケなどのスポーツでジャンプして着地する際に膝を内側に捻って起こることが多いです。
前十字靱帯断裂の診断
前述のように中高生くらいの女性が膝を捻って受傷し、膝に強い痛みと腫れがあれば疑います。
診察で膝のぐらつき感を触知できる場合もあります。
レントゲンでは確定診断はできず、MRIにて行います。
前十字靱帯断裂の治療
前十字靱帯が断裂した場合は、自然治癒は見込めません。
手術にて靱帯再建術を行います。
足首をひねった
診療案内「足首をひねった」をご覧ください。
アキレス腱断裂
アキレス腱断裂とは
アキレス腱は、ふくらはぎからかかとをつないでいる腱になります。
アキレス腱断裂は、このアキレス腱が切れてしまう状態です。
この腱は足首の動きを制御する役割を果たしており、断裂すると歩行や運動に支障をきたすことがあります。
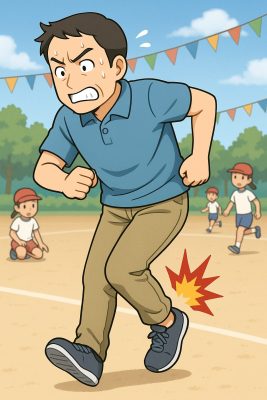
アキレス腱断裂の症状
アキレス腱断裂の症状は、足首の後方の急激な痛みが多いです。
たまに「ブチッ」と腱が切れた音を自覚する場合もあります。
歩行時に足を地面につける際に痛みを伴うことがあります。
また、足首の動きやつま先立ちが困難になります。
アキレス腱断裂の原因
30~40代の方でスポーツによる発症が多いです。
久しぶりにスポーツをされた方が、ジャンプ、着地、踏み込みの動作などが原因で、前述の症状を自覚することが多いです。
アキレス腱断裂の診断
スポーツをしている時に足首の後方が痛くなったなどの特徴的なエピソードがあれば疑います。
多くの場合はアキレス腱の部分に凹みを触れ、その部分に痛みを伴います。
うつ伏せでふくらはぎを握ると通常は足首が動きますが、動かなければ積極的にアキレス腱断裂を疑います。(Tompson test)
エコーやMRIで、アキレス腱の断裂を確認できれば確定となります。
アキレス腱断裂の治療
手術しない治療と手術する治療があります。
いずれの場合もスポーツへの復帰には長い時間がかかり、リハビリも慎重に行う必要があります。
手術する治療としない治療いずれもメリット、デメリットがあります。
手術しない治療
超音波にて、腱の断端(切れ端)が接触していることが確認できれば、手術せずに腱がくっつく可能性があります。
足首をギプスにて固定し、その後アキレス腱への負担を軽減する装具を使用して治療する方法になります。
メリットは手術を回避することができる点、感染症などの手術の合併症を避けることができる点があります。
デメリットは腱がくっつく可能性が100%ではない、再断裂する可能性が手術よりも高い点が挙げられます。
手術する治療
アキレス腱を縫い合わせる手術になります。
メリットは固定期間短くなる可能性がある(手術でどの程度しっかり縫合できたかによっても変わります)、再断裂する可能性が低くなる点があります。
デメリットは感染症などの手術による合併症の可能性がある、リハビリ開始まで時間がかかる可能性がある点が挙げられます。
手術するかしないかはそれぞれのメリット、デメリットを踏まえて検討して頂く必要があります。
ジャンパー膝
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)とは
ジャンパー膝(膝蓋腱炎)は、バレーボール、バスケットボール、陸上競技などジャンプ動作を繰り返すスポーツ選手に多く見られる膝のスポーツ障害です。
膝のお皿(膝蓋骨)からすぐ下の膝蓋腱という部分に負担がかかり、炎症や微小な損傷が生じて痛みを引き起こします。
スポーツ選手だけでなく、繰り返しの階段昇降やジャンプ動作の多い方にも見られます。
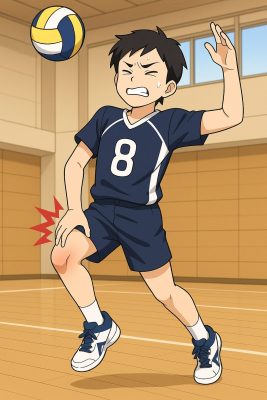
ジャンパー膝の症状
ジャンパー膝では、膝のお皿のすぐ下に痛みが出るのが特徴です。
スポーツ中やジャンプの際に痛みが強くなることが多く、運動を始めたときには痛みが軽くても、運動後や翌日に痛みが増すことがあります。
症状が進行すると、安静にしていても痛みを感じるようになることがあります。
ジャンパー膝の原因
ジャンパー膝の主な原因は、ジャンプや着地動作の繰り返しにより膝蓋腱に過剰な負担がかかることです。
大腿四頭筋(太ももの筋肉)の柔軟性不足や筋力のアンバランス、トレーニング量の急激な増加、硬い床での運動なども発症の要因となります。
特にスポーツの動作による負担が大きく影響している場合が多いです。
ジャンパー膝の診断
ジャンパー膝の診断は、まず問診で痛みが出たきっかけや運動状況を確認し、膝蓋骨のすぐ下を押したときに痛みがあるかどうかを調べます。
また、ジャンプや踏み込み、スクワットなどの動作で痛みが再現されるかをみることで診断の参考にします。
必要に応じて、超音波検査やMRIなどの画像検査を行い、腱の炎症や損傷の程度を確認することもあります。
ジャンパー膝の治療
治療は保存療法が中心になります。
痛みが強い場合はスポーツやジャンプ動作を控えて膝蓋腱への負担を軽減します。
リハビリで大腿四頭筋やハムストリングスといった太ももの筋肉をストレッチして柔軟性を高め、筋力トレーニングを行うことで膝周囲の安定性を高めます。
また、膝蓋腱バンド(パテラバンド)を使用して腱の負担を軽減させる方法や、温熱療法や超音波治療などの物理療法、消炎鎮痛薬の使用も検討されます。
当院では、保存療法で症状がなかなか改善しない方や長期間痛みが続く方に対して、集束型体外衝撃波治療も行っています。
この治療法は、膝蓋腱の痛みがある部分に衝撃波を照射することで痛みを軽減し、組織の修復を促す効果が期待されます。
ジャンパー膝は、適切なストレッチや運動量の調整、物理療法、そして必要に応じて集束型体外衝撃波治療を組み合わせることで改善が期待できます。
集束型体外衝撃波治療に関しては、当院の診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
シンスプリント
シンスプリントとは
シンスプリントは、運動を繰り返すことで、すねの内側(脛骨の内側)に痛みが出るスポーツ障害です。
特にランニングやジャンプ動作の多いスポーツを行う方に多く見られ、陸上競技、バスケットボール、サッカー、ダンスなどをしている方がよく悩まされるケガの一つです。
運動時のオーバーユース(使いすぎ)によって、すねの骨を支える筋肉や骨膜に負担がかかり、炎症が起こることで痛みが発生します。

シンスプリントの症状
シンスプリントの主な症状は、すねの内側の下の方に痛みや違和感を感じることです。
運動を始めるときや走っている途中に痛みが現れ、運動を中止すると痛みが和らぐことが多いですが、症状が進行すると安静時や歩行時にも痛みが出るようになります。
痛みを放置して運動を続けると、疲労骨折へ進行することもあるため、早めの対処が大切です。
シンスプリントの原因
シンスプリントの原因は、繰り返しのランニングやジャンプ動作によるすねの内側への負担が大きく影響しています。
特に、急激に運動量を増やしたり、硬い路面でのランニングを行ったり、クッション性の少ないシューズを使用したりすることが発症の要因になります。
また、足のアライメント不良(扁平足や回内足)や、ふくらはぎの筋肉の柔軟性不足も負担を増やす原因となります。
シンスプリントの診断
診断は、まず問診で運動習慣や痛みが出るタイミングを詳しく伺い、触診で痛みが出る部位を確認します。
典型的には、すねの内側の下3分の1あたりを押すと痛みがあり、運動時に痛みが再現されることが診断の手がかりになります。
必要に応じて、X線やMRI検査を行い、重症度の確認や疲労骨折などの他の疾患との鑑別を行います。
シンスプリントの治療
治療の基本は、運動量の調整と休息をとり、痛みのある部位の負担を減らすことです。
MRIで炎症が強い場合は一時的にランニングやジャンプ動作を中止し、患部を冷やして炎症を抑えます。
また、ふくらはぎの筋肉のストレッチを行って柔軟性を高め、負担を減らすことが大切です。
再発防止のためには、筋力トレーニングやフォームの見直し、クッション性の高いシューズの使用、インソールの活用なども検討します。
当院では、慢性的に痛みが続く方や保存療法だけではなかなか改善しない方に対して、集束型体外衝撃波治療を導入しています。
集束型体外衝撃波治療は、痛みがある部分に衝撃波を照射し、痛みをとり、組織の修復を促す治療法です。
シンスプリントによる痛みを和らげるだけでなく、骨膜の治癒をサポートする効果が期待できます。
集束型体外衝撃波治療に関しては、診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
アキレス腱炎
アキレス腱炎とは
アキレス腱炎は、かかとの後ろからふくらはぎにかけて伸びているアキレス腱に炎症が起こり、痛みや腫れを引き起こす病気です。
ランニングやジャンプなどのスポーツをしている方に多く見られるほか、普段あまり運動をしていない方でも急に運動を始めたり、歩きすぎたりすることで発症することがあります。

アキレス腱炎の症状
アキレス腱炎の主な症状は、アキレス腱部分の痛みや腫れ、熱感です。
特に運動を始めたときや歩き出すときに痛みを感じやすく、運動を続けると痛みが強くなることがあります。
朝起きたときの一歩目が特に痛むこともあり、症状が進むと安静にしていても痛みが続くことがあります。
アキレス腱炎の原因
アキレス腱炎の原因は、アキレス腱に過度の負担がかかることです。
特にランニングやジャンプ動作の繰り返し、急激な運動量の増加、硬い路面での運動、クッション性の低い靴の使用などが大きく影響します。
また、ふくらはぎの筋肉の柔軟性不足や、アキレス腱の加齢による変性も関与している場合があります。
アキレス腱炎の診断
診断は、問診で痛みが出たきっかけや運動の状況を詳しく伺い、アキレス腱の痛みや腫れ、圧痛(押したときの痛み)を確認します。
また、つま先立ちをすると痛みが強くなることも診断の参考になります。
必要に応じて、超音波検査やMRI検査を行い、腱の炎症や断裂の有無を確認します。
アキレス腱炎の治療
治療の基本は、まずアキレス腱への負担を減らすことです。
痛みが強い場合は、運動を一時的に中止して安静を保ちます。
アイシングや湿布で炎症を抑えたり、ヒールパッドを使用してアキレス腱への負担を軽減したりする方法もあります。
痛みが和らいできたら、ふくらはぎの筋肉のストレッチやアキレス腱の柔軟性を高めるリハビリを行い、再発防止に努めます。
当院では、なかなか改善しないアキレス腱炎の方や、より早い回復を希望される方に対して、集束型体外衝撃波治療を導入しています。
集束型体外衝撃波治療は、痛みのあるアキレス腱部分に衝撃波を照射することで痛みを軽減し、組織の修復を促す効果が期待されます。
これにより、痛みの軽減だけでなく、回復のスピードアップが期待できます。
集束型体外衝撃波治療に関しては、診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
疲労骨折
疲労骨折とは
疲労骨折は、骨に繰り返し負担がかかることで起こる小さなひび割れのことをいいます。
特に、スポーツや長時間の歩行、ランニングなどで同じ動作を繰り返す方に多くみられます。
転倒や大きな衝撃で起こる通常の骨折とは異なり、日常的な動作や運動の中で少しずつダメージが蓄積されて発症します。

疲労骨折の症状
疲労骨折の主な症状は、運動中や運動後に感じる痛みです。
最初は運動時だけの痛みでも、症状が進行すると安静時や歩行時にも痛みが現れるようになります。
腫れや熱感を伴うこともあり、患部を押すと痛みを感じる場合もあります。
痛みを我慢して運動を続けると、完全な骨折に至る恐れがあるため注意が必要です。
疲労骨折の原因
疲労骨折の原因は、骨への繰り返しの負担です。
急激に運動量を増やしたり、硬い路面でランニングしたり、クッション性の少ないシューズでトレーニングを行ったりすることで、骨に小さな損傷が繰り返され発症します。
また、筋力不足や柔軟性の低下、栄養不足(特にカルシウムやビタミンD)も疲労骨折のリスクを高めます。
よくある疲労骨折の種類
疲労骨折は全身のさまざまな部位に起こりますが、特に多いのは下肢です。
脛骨(すねの骨)や腓骨(すねの外側の骨)、中足骨(足の甲の骨)、足根骨(足の甲の骨)などがよく見られます。
スポーツの種類によっても違いがあり、陸上競技の長距離ランナーでは脛骨や中足骨、バスケットボール選手では足根骨などが好発部位です。
疲労骨折の診断
診断は、まず問診で痛みの出方や運動歴を詳しく伺い、痛みの部位を触診して確認します。
初期の疲労骨折はレントゲンでは写りにくい場合もありますが、MRIを行うことで、骨の炎症や骨折の有無を詳しく調べることができます。
疲労骨折の治療
治療の基本は、患部への負担を減らして安静にすることです。
痛みが出る運動を中止し、必要に応じて松葉杖や装具を使用して患部への負担を軽減します。
痛みが和らいできたら、ストレッチや筋力トレーニングを行い、再発防止に努めます。
当院では、なかなか痛みが改善しない場合やより早い回復を希望される方に対して、集束型体外衝撃波治療を導入しています。
集束型体外衝撃波治療は、骨や周囲の組織に衝撃波を照射し、骨の修復をサポートする治療法です。
痛みの軽減や治癒の促進が期待でき、疲労骨折の回復をサポートします。
集束型体外衝撃波治療に関しては、診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
ハムストリングス肉離れ
ハムストリングス肉離れとは
ハムストリングス肉離れは、太ももの裏側にある筋肉「ハムストリングス」が急に伸ばされたり、強い力で引っ張られて損傷するケガです。
走ったりジャンプしたりする動作中によく起こり、スポーツ中のケガとしてとても一般的です。
特にウォーミングアップ不足や疲労がたまっているときに起こりやすく、急な動き出しなどがきっかけになります。

ハムストリングス肉離れの症状
突然の鋭い痛みとともに、太ももの裏側に「ブチッ」という感覚を覚えることがあります。
痛みが強く、歩くことが難しくなる場合もあります。
損傷の程度によっては、腫れや内出血が見られることもあります。
筋肉の断裂が大きい場合は、触るとへこみのような感触があることもあります。
ハムストリングス肉離れの原因
主な原因は、筋肉に急激な負荷がかかることです。
運動不足の状態で急に全力で走ったり、冷えた筋肉で無理な動きをすると、筋肉が伸びすぎて損傷してしまいます。
特にスポーツでのダッシュやキックの動作、急な方向転換はリスクが高く、再発もしやすいケガです。
ハムストリングス肉離れの診断
医師による診察では、患部の痛みの位置や腫れ、筋肉の動きをチェックします。
必要に応じて超音波(エコー)やMRI検査を行い、どの程度の筋肉損傷があるかを詳しく確認します。
これにより、軽度〜重度までの分類(1度〜3度)を行い、治療の方針や復帰時期の目安を立てていきます。
ハムストリングス肉離れの治療と復帰までの目安
治療は、損傷の程度によって異なります。
軽度の肉離れであれば、まずは患部を安静に保ち、冷却や圧迫、挙上(RICE処置)を行います。
数日〜1週間ほどで痛みが落ち着いてきたら、徐々にストレッチや軽い筋力トレーニングを始めていきます。
中等度以上の損傷では、回復までに数週間〜2ヶ月程度かかることもあります。
リハビリでは、筋肉の柔軟性やバランスを整えながら、再発を防ぐことを目的に段階的にトレーニングを行っていきます。
痛みがなくなっても、焦って元の運動量に戻すと再発のリスクが高まるため、慎重な復帰が必要です。
復帰の目安としては、
・軽度の肉離れ:2〜3週間で日常生活や軽い運動への復帰が可能
・中等度:3〜6週間程度で運動復帰が視野に入る
・重度:2〜3ヶ月以上かかる場合もあり、手術が検討されることもあります
また、当院では拡散型圧力派を導入しており、早期復帰を目指す方のハムストリングス肉離れは良い適応となります。
医師の判断とリハビリの進行を見ながら、無理のない範囲で復帰時期を決めていくことが大切です。
腓腹筋肉離れ
腓腹筋肉離れとは
腓腹筋肉離れとは、ふくらはぎの表面にある「腓腹筋(ひふくきん)」という筋肉が急激な動きや負荷によって部分的に断裂してしまうケガのことをいいます。
腓腹筋は膝の裏からアキレス腱までをつなぐ大きな筋肉で、歩く・走る・ジャンプするなど、日常動作からスポーツまでさまざまな動きに関わっています。
特に中高年の方がスポーツをしているときに起こりやすく、「テニスレッグ」という名前で呼ばれることもあります。

腓腹筋肉離れの症状
ふくらはぎに突然「ブチッ」という音や強い衝撃を感じ、その場で動けなくなるほどの鋭い痛みが走ります。
受傷直後には歩行が困難になることもあり、ふくらはぎに腫れや内出血が現れることもあります。
痛みの程度には個人差がありますが、筋肉に力を入れたり、つま先立ちをしようとしたときに再び強い痛みが出ることが特徴です。
軽度であっても放置すると回復が長引くことがあるため、早めの対応が重要です。
腓腹筋肉離れの原因
主な原因は、筋肉が急激に引き伸ばされることで、筋線維に損傷が起こることです。
準備運動が不十分な状態で急に全力疾走したり、ジャンプ動作をしたりすると、腓腹筋に大きな負荷がかかり、肉離れが発生します。
特にテニスやバドミントン、サッカー、陸上競技などで多く見られます。
また、中高年では筋力や柔軟性の低下により、日常のちょっとした動作でも起こることがあります。
腓腹筋肉離れの診断
診察では、痛みの部位や腫れ、筋肉の動きなどを丁寧に確認します。
患部を押すと強い痛みがあり、筋肉の緊張やへこみが感じられることもあります。痛みの強さや腫れの広がり具合などから、損傷の程度をおおよそ判断できます。
必要に応じて超音波検査(エコー)を行い、筋肉の断裂の範囲や深さを視覚的に確認することで、より正確な診断が可能です。
超音波でもわかりにくい場合は、MRIを撮影する場合もあります。
腓腹筋肉離れの治療
治療の基本は、まず炎症と痛みを抑えるために安静を保つことです。
受傷直後は患部を冷やし、包帯やテーピングで圧迫しながら足を心臓より高く上げて休ませる「RICE処置」が有効です。
軽度の場合は数日から1〜2週間で痛みが引き、徐々に日常生活へ復帰できます。
中等度以上の肉離れでは、数週間にわたって松葉杖を使って負荷を避けながら回復を待ち、その後にストレッチや筋力トレーニングなどのリハビリを行います。
痛みが落ち着いた後も、急に以前の運動量に戻すと再発のリスクが高くなります。
再発防止のためには、ふくらはぎの柔軟性と筋力のバランスを整えることが重要です。
まれに大きな筋断裂がある場合には、外科的処置が検討されることもありますが、多くの場合は保存的治療で改善が見込めます。
腸脛靭帯炎
腸脛靭帯炎とは
腸脛靭帯炎は、膝の外側にある「腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)」という強い靭帯が炎症を起こして、膝の外側に痛みが出る疾患です。
腸脛靭帯は、骨盤の外側から太もも、膝の外側を通って脛の骨(すね)につながる長くて丈夫な靭帯で、膝を安定させる働きをしています。
この靭帯が、膝の外側の骨と繰り返し擦れることで炎症が起こり、痛みの原因になります。
特に長距離ランナーや自転車競技、登山、ハイキングをする方に多く見られるため、「ランナー膝」とも呼ばれます。

腸脛靭帯炎の症状
もっとも特徴的な症状は、膝の外側の痛みです。
運動を始めてしばらくすると痛みが出てきて、さらに運動を続けるとどんどん痛みが強くなる傾向があります。
特に、階段を下りる動作や坂道を走るときなど、膝の屈伸が繰り返される動作で痛みが悪化しやすくなります。
症状が進行すると、日常生活の中でも違和感や痛みを感じるようになり、運動を中断せざるを得なくなることもあります。
腸脛靭帯炎の原因
腸脛靭帯炎の主な原因は、膝の屈伸を繰り返すことによる「腸脛靭帯と大腿骨外側の骨突起との摩擦」です。
これが続くことで炎症が起こり、痛みにつながります。特にランニングやサイクリングなどで長時間膝を動かし続けると、靭帯にストレスがかかりやすくなります。
また、フォームの乱れや柔軟性の低下、筋力のアンバランス、硬い路面での運動、シューズが合っていないことなども発症を助長する要因です。
腸脛靭帯炎の診断
診察では、膝の外側を押したときに痛みがあるか、膝の曲げ伸ばしで痛みが再現されるかを確認します。
患者さんの運動習慣や痛みが出るタイミング、歩行や走り方の癖なども重要な情報になります。
必要に応じて、超音波(エコー)検査やMRIを行い、炎症の程度や他の膝の病気との区別をつけることもあります。
腸脛靭帯炎は比較的よく見られる運動障害であり、問診と理学的所見で診断がつくことが多いです。
腸脛靭帯炎の治療
治療の基本は、炎症を抑えることと、原因となる動作の見直しです。
まずは運動を一時的に休止し、患部の安静を保ちます。
痛みが強い場合には、アイシングや消炎鎮痛薬の使用が有効です。
また、ストレッチやマッサージを通して、腸脛靭帯や周囲の筋肉(特に大腿筋膜張筋や臀筋)の柔軟性を高めることも治療の一環となります。
再発防止や根本改善のためには、筋力バランスの調整やランニングフォームの修正が必要です。
必要に応じて、理学療法士の指導のもとでリハビリを行い、股関節や体幹の安定性も高めていきます。
慢性化してしまった場合でも、継続的なリハビリによって改善が見込める疾患ですので、焦らずしっかりと治療に取り組むことが大切です。
文責 上田 英範
(日本整形外科学会整形外科専門医)



