股関節が痛い
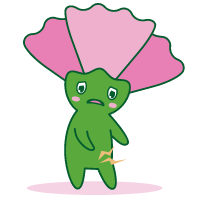
目次 contents
変形性股関節症
変形性股関節症とは
変形性股関節症は、股関節の軟骨がすり減ることで関節の骨の変形が進み、痛みや股関節の動く範囲の制限が生じる病気です。
特に中高年の女性に多く見られ、進行すると日常生活に支障をきたすことがある病気です。

変形性股関節症の症状
初期の症状は、歩行時の股関節の痛み、動く範囲の制限が挙げられます。
変形が進行してくると、安静時の疼痛や動く範囲の制限が強くなり、日常生活に支障が生じるようになります。
また、足の長さに差が出ることもあります。
変形性股関節症の原因
日本人の変形性股関節の原因は、ほとんどが臼蓋形成不全が原因となります。
股関節は大腿骨に骨盤の骨が屋根のようにかぶような構造になっています。
骨盤の骨のかぶさりが先天的に浅い病気を臼蓋形成不全といいます。
臼蓋形成不全がある方は、男性よりも女性が多く、そのため女性の方が変形性股関節症の発生が多くなります。
発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)という、新生児期に起こる股関節の脱臼も原因となる可能性があります。
その他には、加齢、肥満、股関節の骨折、化膿性股関節炎などの股関節の感染も原因となります。
変形性股関節症の診断
問診にて股関節の痛みを訴え、診察で股関節の痛みや動きの制限があるようであれば疑います。
進行した変形性股関節症は、レントゲン検査で十分に診断可能です。
しかし、初期の変形性股関節症の診断はレントゲンでは難しい可能性があり、MRIなどの検査を行う可能性もあります。
変形性股関節症の治療
初期の場合は、保存的治療(手術をしない治療)を行います。
薬物療法、筋力トレーニングや動かす訓練などのリハビリを行い、痛みを抑えます。
筋力訓練は、股関節の変形が進行したとしても疼痛を軽減できる可能性があるため、非常に重要です。
また、体重管理などの生活習慣の改善も非常に重要です。
痛みが強い場合は、手術治療が必要になります。
股関節の変形が軽度で、若い方には骨切り術という手術が適応になることがあります。
骨切り術は、骨盤や大腿骨の骨を切って繋ぎ直すことで、形を変えて痛みを取る手術です。
変形が強く、若年者ではない場合は、人工股関節置換術(THA)の適当となります。
人工股関節置換術は、股関節を形成する大腿骨、骨盤の骨を切って取り除き、金属に入れ替える手術です。
人工股関節には耐用年数があり、15年〜20年程度と言われております。
できる限り手術時期は遅らせることがベストではありますが、痛みと体の状態を見極めながら時期を決めることが大切です。
大腿骨頭壊死症
大腿骨頭壊死症(だいたいこっとうえししょう)とは
大腿骨頭壊死症は、大腿骨の骨頭(大腿骨の上部)への血流が途絶えることで、骨が壊死(細胞が死んでしまう状態)する病気です。
壊死が進行すると、骨頭の形が崩れて股関節の機能が低下し、強い痛みや歩行障害が生じることがあります。
特に40~60代の方に多く見られますが、若年層でも発症することがあります。
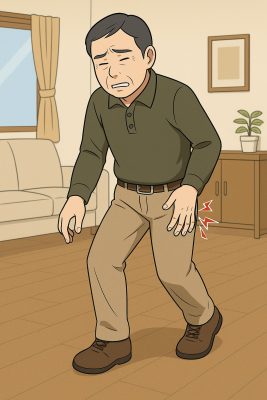
大腿骨頭壊死症の症状
初期は、股関節や鼠径部(そけいぶ:足の付け根)の違和感や軽い痛みから発症します。
症状が進行すると、安静時でも強い痛みが出現します。
骨頭の壊死が進行し股関節の変形が起こると、股関節の動く範囲が少なくなってきます。
最終的には、歩行が困難になり、日常生活に大きな支障をきたすことになります。
大腿骨頭壊死症の原因
大腿骨頭壊死症は、原因が特定できる場合と、原因が不明な場合(特発性:とくはつせい)があります。
原因が特定できる場合
ステロイドの使用歴がある(特に高用量・長期間)
大量の飲酒歴
外傷(大腿骨頚部骨折や股関節脱臼による血流障害)
原因が不明な場合
この場合は特発性大腿骨頭壊死症といいます。
大腿骨頭壊死症の診断
股関節の疼痛と動きの制限があり、ステロイドの使用歴や大量の飲酒歴があれば疑います。
進行した症例では、骨頭の圧壊や変形がレントゲン検査で確認できますが、初期では異常が見られないこともあります。
レントゲン検査で特に異常所見が見られない場合、MRI検査を行うことで、大腿骨頭に特徴的な異常所見を認めれば確定診断となります。
大腿骨頭壊死症の治療
治療法は、症状の程度や壊死の進行度によって選択されます。
保存治療(手術をしない治療)としては、まず大量飲酒歴があれば、飲酒を控えたり、体重管理を行います。
その上で、鎮痛薬などの薬物療法、股関節周囲の筋力強化を目的として運動療法を中心としたリハビリを行います。
症状が強い症例では手術治療が検討されます。
壊死が軽度の場合は、壊死した部分に荷重がかからないように骨を切って調整する骨切り術が適応となります。
壊死が重度の場合は、股関節を金属に入れ替える人工股関節置換術(THA)が選択されます。
大腿骨近位部骨折
大腿骨近位部骨折(だいたいこつきんいぶこっせつ)とは
大腿骨近位部骨折とは、大腿骨(太ももの骨)の股関節に近い部分が折れる骨折のことを指します。
大腿骨近位部骨折は、大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折を含めた総称となります。
特に高齢者の転倒によって発生することが多く、寝たきりの原因となる重大な骨折の一つです。
日本の高齢社会の到来に伴い、非常に問題となっている骨折です。

大腿骨近位部骨折の症状
転倒後から強い股関節の疼痛があり、歩行不能となることがほとんどです。
骨折部がずれると、足が短く見えたり、不自然な方向で外側に向いていることもあります。
大腿骨近位部骨折の原因
ほとんどが高齢者の転倒により起こります。
特に高齢の女性で骨粗鬆症がある方は、わずかな転倒でも骨折が起こります。
まれに非常に強い骨粗鬆症がある方は、転倒の既往がなく歩行しているだけで骨折することがあります。
若年者に起こる場合は、交通事故や高所転落などの強い力がかかる場合、この部位が骨折することがあります。
大腿骨近位部骨折の診断
高齢の女性の方が、転倒後から股関節の痛みや歩行不能がある場合は疑います。
多くの場合は、レントゲン検査で骨折部が確認できます。
まれにレントゲン検査で異常を認めない場合は、MRIが必要になることがあります。
骨折の状態を確認するためにCTが必要になることもあります。
大腿骨近位部骨折の治療
基本的にできる限り早期に手術を行い、早期回復を目指すことが第一選択となります。
大腿骨頚部骨折で骨折部のずれが少ない場合、スクリューやピンで骨折部の固定を行います。
大腿骨頚部骨折で骨折部のずれが大きい場合、骨を金属に入れ替える人工骨頭置換術(BHA)や人工股関節置換術(THA)が行われます。
大腿骨転子部骨折の場合、髄内釘(ずいないてい)やプレートとスクリューによる骨折部の固定を行います。
持病などにより手術ができない場合、保存療法(手術しない治療)が選択されます。
骨折部が安定するまで床上安静、その後リハビリが基本方針となります。
しかし、手術しない場合、骨がくっつかなかったり、骨がくっついても床上安静が非常に長期間になるため、寝たきりになる可能性が高くなります。
大腿骨近位部骨折の予後
大腿骨近位部骨折の1年以内の死亡率は日本では10%前後、海外では10〜30%と報告されています。
大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン2021 改定第3版
非常に予後が悪い骨折であるため、骨折しないように転倒予防、骨粗鬆症の予防が大切となります。
単純性股関節炎
単純性股関節炎とは
単純性股関節炎とは、お子さまの股関節に一時的な炎症が起こり、股関節や太ももに痛みが出る疾患です。
3歳〜10歳くらいの男の子にやや多く見られますが、女の子にも起こることがあります。
炎症は一時的なもので、多くの場合は1〜2週間で自然に治る「一過性の関節炎」であり、予後は良好です。
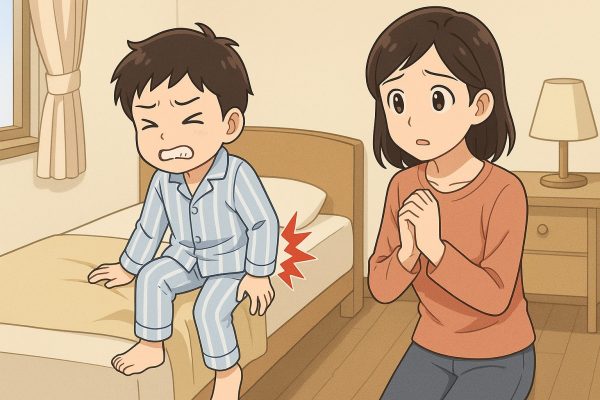
単純性股関節炎の症状
主な症状は、股関節の痛みや違和感です。
痛みの程度はさまざまで、軽い違和感だけの場合もあれば、足を引きずるほど強い痛みが出ることもあります。
太ももや膝の痛みとして感じられることもあるため、初めは膝の病気と間違えられることもあります。
また、痛みのために歩くのを嫌がったり、片足をかばうような歩き方をしたりすることがあります。
発熱はないか、ごく軽い微熱が出ることもあります。
単純性股関節炎の原因
正確な原因ははっきりとはわかっていませんが、まれに、風邪などのウイルス感染の後に発症することがあります。
体の免疫反応によって股関節に一時的な炎症が起こるのではないかと考えられています。
細菌による感染性の関節炎とは異なり、関節が破壊されるようなことはなく、自然に回復していくのが特徴です。
単純性股関節炎の診断
診察では、お子さまの歩き方や股関節の動きを丁寧に確認します。
股関節を動かしたときに痛がることが多く、動きが制限されているかどうかをチェックします。
必要に応じてレントゲン検査や超音波検査を行い、股関節の中に少量の関節液(関節の中の水)がたまっている様子が見られることもあります。
感染性股関節炎など重篤な疾患との区別が重要なため、初期評価では慎重な判断が求められます。
単純性股関節炎の治療
治療の基本は安静です。
無理に歩かせたり、痛みを我慢させたりせず、痛みが和らぐまでしっかりと休ませることが大切です。
痛みが強い場合には、必要に応じて解熱鎮痛薬を使用することもありますが、多くの場合は薬を使わずに経過を見ていくことができます。
通常、1週間ほどで痛みが改善し、2週間以内には普段通りに歩けるようになることがほとんどです。
まれに痛みが長引いたり、他の疾患が隠れている可能性もあるため、症状が改善しない場合は再評価が必要です。
ペルテス病
ペルテス病とは
ペルテス病とは、股関節にある「大腿骨頭(だいたいこっとう)」という太ももの骨の先端部分に血液が届きにくくなり、一時的に壊死(骨が死んでしまうこと)を起こす病気です。
壊死した骨は徐々に体の自然な力で吸収され、新しい骨が再び作られていくという流れをたどりますが、その過程で骨の形が変形し、股関節の動きに支障が出ることがあります。
主に4〜10歳頃の男の子に多く見られ、成長期に発症することが特徴です。
多くの場合は片側の股関節に発症しますが、まれに両側にみられることもあります。
早期発見と適切な治療によって、関節の機能を守ることが可能です。

ペルテス病の症状
最初のサインとして、股関節や太もも、あるいは膝の痛みが出てくることがあります。
お子さま自身が膝の痛みを訴えることが多いため、股関節の異常だとは気づかれにくいことがあります。
また、痛みのために足を引きずるように歩いたり、走らなくなったり、座っていることが多くなるなど、歩き方や動作に変化が現れます。
症状は日によって強くなったり軽くなったりすることもあり、初期には見逃されがちですが、進行すると可動域が狭くなり、脚の長さに左右差が出ることもあります。
ペルテス病の原因
ペルテス病の原因はまだはっきりとはわかっていませんが、成長期の子どもに特有の血流障害が関係していると考えられています。
大腿骨頭への血液供給が一時的に低下することで、骨が栄養を失い壊死に至るとされています。
遺伝やホルモン、外傷、血液凝固異常などさまざまな要因が複雑に関与しているとされますが、特定の一因に絞ることはできません。
ペルテス病の診断
診察では、股関節の動きや痛みの有無、歩き方などを確認します。
X線(レントゲン)検査で骨頭の変化を確認することが基本ですが、発症直後の初期段階ではレントゲンに変化が出ないこともあり、その場合はMRI検査が非常に有効です。
MRIでは血流の変化や骨の壊死の兆候を早期に捉えることができます。
診断後は、骨の変形の程度や進行状況を定期的にモニタリングしながら、治療方針を決定していきます。
ペルテス病の治療
治療の目標は、再生される骨ができるだけ元の丸い形に近い形で回復するように導くことです。
変形したまま治ってしまうと、将来的に股関節の動きが悪くなったり、関節症の原因になることがあるため、早期からの適切な対応が重要です。
治療方法は、年齢や病気の進行度、骨の変形の有無によって異なります。
比較的軽症であれば、股関節への負担を減らすために安静にしたり、運動を制限したりします。
歩くときには杖や松葉杖、装具(ブレース)を使って体重をかけないようにすることもあります。
必要に応じて、ストレッチや理学療法で股関節の柔軟性を保つリハビリを行います。
骨の変形が進んでいたり、保存療法での改善が見込めない場合は、外科的治療(骨切り術など)が検討されることもあります。
どの治療を行う場合でも、数か月から数年にわたっての経過観察が必要になるため、根気よく治療を続けていくことが大切です。
大腿骨頭すべり症
大腿骨頭すべり症とは
大腿骨頭すべり症とは、成長期の子どもに起こる股関節の病気で、大腿骨(太ももの骨)の先端にある骨頭部分が、骨の成長板(骨端線)を境に後ろや下の方向にずれてしまう状態です。
骨がずれることで股関節の動きが悪くなり、痛みや歩行の異常が現れます。通常、10歳〜15歳の思春期の男の子に多く見られ、両側の股関節に起こることもあります。
放っておくと、股関節が変形したまま治ってしまい、大人になってから関節の機能障害や変形性股関節症を引き起こすことがあります。
そのため、早期発見と早期治療がとても大切な病気です。

大腿骨頭すべり症の症状
最もよくみられる症状は、股関節や太もも、膝にかけての痛みです。
特に膝の痛みを訴えるケースが多く、膝の異常と間違えられることもあります。
また、歩くときに足を引きずるようになったり、片足に体重をかけづらくなるなど、歩行の異常が目立ってくることもあります。
ゆっくりと進行する「慢性型」の場合は、徐々に股関節の動きが悪くなり、あぐらをかくような動きができなくなってきます。
一方で、急激に進行する「急性型」では、急に痛みが強くなり、まったく歩けなくなるようなケースもあります。
大腿骨頭すべり症の原因
この病気は、骨が急速に成長する時期に発症することが多く、骨頭と骨幹(骨の中心部)をつなぐ成長板の部分が一時的に弱くなることで、骨頭が滑りやすくなってしまうと考えられています。
体重が増加傾向にある子どもや、ホルモンバランスに異常がある場合にも発症リスクが高まることがあります。
また、軽いケガや日常の運動がきっかけで発症することもあり、必ずしも激しい外傷がなくても発症するのが特徴です。
大腿骨頭すべり症の診断
診察では、股関節の動きや歩き方、脚の長さの左右差などを確認します。
特に股関節の内旋(足を内側に回す動き)が制限されている場合には、この病気を疑います。
確定診断にはX線(レントゲン)検査が非常に重要で、骨頭の位置がずれていないかを正面や側面から確認します。
必要に応じてMRIやCT検査を行い、詳細な骨の状態や軟骨の損傷を調べることもあります。
大腿骨頭すべり症の治療
大腿骨頭すべり症は、自然に治ることはないため、早期に治療を始める必要があります。
基本的には、骨頭がこれ以上ずれないようにするために手術で固定を行います。
具体的には、骨頭と骨幹を金属のスクリュー(ネジ)でしっかりと固定し、成長板のすべりを止める処置が一般的です。
手術は通常、患部をできるだけ安定させ、将来的な股関節の変形や機能障害を防ぐことを目的とします。
手術後は、数週間から数か月にわたり、体重のかけ方や歩行訓練などのリハビリが必要となります。
また、反対側の股関節にも同じ病気が起こるリスクがあるため、定期的な経過観察が欠かせません。
文責 上田 英範
(日本整形外科学会整形外科専門医)

