手がしびれる
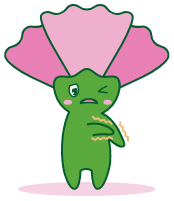
目次 contents
手根管症候群
手根管症候群とは
手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)は、手首の内側にある「手根管」と呼ばれる狭いトンネルの中で、正中神経という大事な神経が圧迫されることによって起こる病気です。
この神経は、手のひらの感覚や親指を動かす筋肉とつながっており、神経が圧迫されると手のしびれや痛み、動かしにくさが出てきます。
手をよく使う方や、更年期の女性、妊娠中の方に多く見られるのが特徴です。
手がしびれる、指先の感覚が鈍い、といった症状が続く場合には、早めに受診することが大切です。
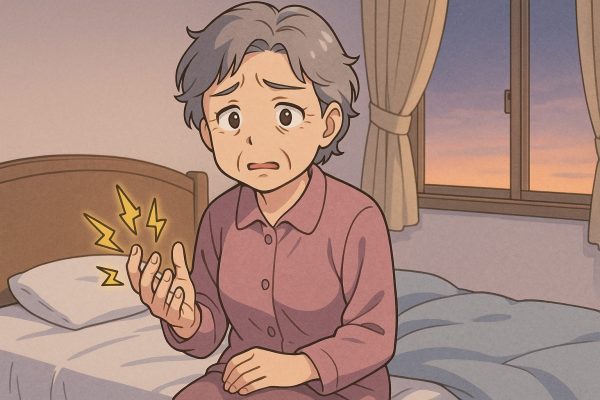
手根管症候群の症状
手根管症候群では、親指、人差し指、中指、薬指の半分にかけてしびれや痛みが現れることが多く、特に夜間や朝方に症状が強くなる傾向があります。
目が覚めたときに手がしびれていたり、手を振るとしびれが一時的に楽になることもあります。
症状が進行すると、指先の感覚が鈍くなり、細かい作業がしにくくなったり、ボタンを留めることや箸を使うことが難しくなることがあります。
さらに悪化すると、親指の付け根の筋肉がやせてしまい、力が入りにくくなる場合もあります。
手根管症候群の原因
手根管症候群の原因は、手首の使いすぎや、加齢による手根管内の狭まり、ホルモンバランスの変化などが関係しているといわれております。
家事やパソコン作業、手作業を長時間続けている方にも見られます。
妊娠や更年期、糖尿病、関節リウマチなども発症のきっかけになることがあります。
原因がはっきりしない場合もありますが、手を酷使する生活習慣が大きく関係していることが多いです。
手根管症候群の診断
診断は、まず症状の経過や手のしびれの範囲を詳しくお聞きし、手首を曲げたり(Phalen test)、手のひらをたたく検査(Tinel sign)で神経が刺激されるかどうかを確認します。
必要に応じて、神経の伝わり具合を調べる神経伝導検査を行い、神経がどの程度圧迫されているかを調べます。
場合によっては、他の病気との区別をするために、レントゲンや超音波検査を追加することもあります。
これらの検査により、手根管症候群かどうかをしっかりと見極めていきます。
手根管症候群の治療
手根管症候群の治療は、症状の程度に応じて変わります。
軽い場合は、まずは手首や指の使い過ぎを避けていただきます。
ビタミンB12の処方も行いますが、これだけで良くなることも少なくありません。
症状が強い場合には、手首の手根管に局所麻酔とステロイドの注射を行い、神経の圧迫を和らげる方法を行うこともあります。
もしこれらの治療で十分な改善が見られない場合や、筋肉がやせてしまっている場合には、神経の圧迫を取り除くための手術が必要になることがあります。
術後はリハビリを行いながら手の動きを取り戻していくこともあります。
肘部管症候群
肘部管症候群とは
肘部管症候群(ちゅうぶかんしょうこうぐん)は、肘の内側を通る尺骨神経(しゃっこつしんけい)が圧迫されたり、引き伸ばされたりすることで起こる神経の障害です。
肘の内側、いわゆる「ひじの内側をぶつけたときにビリッとする部分」のあたりで、神経が通るトンネルが狭くなったり、周囲の組織に圧迫されたりすると、手や指にしびれや動かしにくさが出てきます。
気づかないうちに少しずつ進行してしまうこともあるため、早めの受診が大切です。

肘部管症候群の症状
肘部管症候群では、小指と薬指の一部にしびれや違和感を感じることが多く、指先がピリピリしたり、感覚が鈍くなったりすることがあります。
症状が進んでくると、細かいものをつまむ動作がしにくくなったり、物を落としやすくなったりすることがあります。
特に長時間肘を曲げているとしびれが強くなることがあり、寝ている間に肘が曲がったままになると、夜中にしびれで目が覚めてしまうこともあります。
さらに進行すると、小指側の手の筋肉がやせてしまい、指がしっかり動かなくなる場合もあります。
肘部管症候群の原因
肘部管症候群は、日常生活の中で肘を長時間曲げた姿勢を続けることや、デスクワーク、運転、スマートフォンの操作などで肘に負担がかかることが原因になることがあります。
肘の変形や骨折の後遺症、加齢による骨の変化がきっかけになる場合もあります。
野球やテニス、柔道など、肘をよく使うスポーツをしている方にも起こりやすい傾向があります。
中には、肘周りにできたガングリオン(小さなできもの)が神経を圧迫しているケースもあります。
肘部管症候群の診断
診断では、まずしびれや痛みの部位、日常生活での困りごとを丁寧にお聞きします。
診察では、肘の内側をたたいて痺れが出るのを確認します(Tinel sign)。
必要に応じて、レントゲンで骨の変形や異常がないかを調べたり、超音波で神経の圧迫部分を確認することもあります。
さらに、神経の伝わり具合を調べる検査(神経伝導検査)を行うことで、肘部管症候群の重症度を詳しく評価することができます。
肘部管症候群の治療
治療は、症状の程度に合わせて進めていきます。
まずは日常生活で肘を安静にするように指示します。
痛みやしびれが強いときには、ビタミンB12を処方してしびれを軽減する治療を行います。
こうした保存的な治療で症状が改善することもありますが、症状が進んでしまっている場合や、筋力低下が見られる場合には手術が必要になることがあります。
手術では、神経の通り道を広げたり、尺骨神経の位置を移動させたりして、圧迫を取り除く処置を行います。
術後はリハビリを行い、手の動きや感覚の回復を目指します。
早期に治療を始めることで、手の機能をしっかり守ることができます。
文責 上田 英範
(日本整形外科学会整形外科専門医)

