肘が痛い
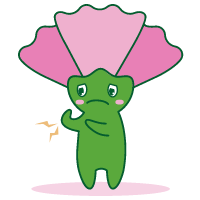
上腕骨外側上顆炎(テニス肘)
上腕骨外側上顆炎(テニス肘)とは
上腕骨外側上顆炎(じょうわんこつがいそくじょうかえん)は、肘の外側に痛みが生じる疾患で、テニス肘とも呼ばれます。
特に手や手首を頻繁に使う人に発症しやすく、テニスなどのスポーツ以外でも発生することがあります。

上腕骨外側上顆炎の症状
肘の外側の痛みが特徴です。
特にペットボトルやフライパンなど物をつかんで持ち上げる動作の時に痛がられることが多いです。
上腕骨外側上顆炎の原因
手や手首の使いすぎにより起こります。
手や手首を動かす筋肉の腱(短橈側手根伸筋、長橈側手根伸筋、総指伸筋)は、全て一緒になって肘の外側にくっついていきます。
その筋肉の腱のくっつく部分が使いすぎにより炎症を起こすことが原因です。
テニスで起こることが多いので、通称テニス肘とも呼ばれますが、経験上、仕事で起こることが最も多い印象です。
その他、年齢に伴って腱が傷んできて起こるとも考えられております。
上腕骨外側上顆炎の診断
肘の外側の疼痛があり、問診で仕事で手をよく使うなどの病歴があれば疑います。
レントゲン検査では、明らかな異常が見られない場合が多いです。
以下のような徒手検査で疼痛があれば上腕骨外側上顆炎と診断できます。
・Tomsen Test:患者さんは肘を伸ばして手首をそらした状態で保持してもらい、医師が手首を逆に曲げる力を加えた時に肘に痛みが出れば陽性です。
・Chair Test:患者さんに肘を伸ばした状態で椅子をつかんで、持ち上げてもらった時に肘に痛みが出れば陽性です。
・中指伸展Test:患者さんは肘を伸ばした状態で中指をそらし、医師が中指を押し下げる力を加えた時に肘に痛みが出れば陽性です。
その他、超音波(エコー)検査で、腱に炎症所見が見られたり、MRIで腱に炎症所見が見られたりするのを確認することもあります。
上腕骨外側上顆炎の治療
まずは保存療法(手術をしない治療)をすることになります。
手と手首の安静を得ていただき、内服、湿布などの薬物療法を行います。
前腕の筋肉の柔軟性を出すためのストレッチを行っていただきます。
その他、ストレッチをさらに行うためのリハビリや熱と振動の力で治療する超音波治療器を使用することがあります。
前腕の筋肉の走行部分をバンドで圧迫するエルボーバンドも使用することがあります。
改善がない場合や疼痛が強い場合は、局所麻酔薬とステロイドを混ぜた注射を打つことがありますが、注射の打ち過ぎは逆に腱の自己修復作用を落とすと言われますので、打ち過ぎには注意が必要です。
症状が強い場合は、手術を行うことがあります。
筋肉の表面にある筋膜を切開することで症状が改善すると言われます。
手術治療になる方はまれでです。
手の使い過ぎなどの原因が除去できないことが多いため、症状は長引くことが多いです。
上腕骨外側上顆炎に対する新しい治療法
上腕骨外側上顆炎に対する新しい治療法として、集束型体外衝撃波治療があります。
皮膚の外から衝撃波を照射することで、痛みを取り、組織を修復する新しい治療法です。
ほとんどの上腕骨外側上顆炎に適応となりますが、特に内服・湿布、リハビリ、超音波治療器などの物理療法を行っても改善しない方には良い適応となります。
ステロイドの注射を継続的に打っている方や最近ステロイドの注射を打ったという方は適応にならない可能性がありますので、ご注意ください。
集束型体外衝撃波治療に関しては、診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)
上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)とは
上腕骨内側上顆炎(じょうわんこつないそくじょうかえん)は、肘の内側に痛みが生じる疾患で、ゴルフ肘とも呼ばれます。
ゴルフのスイング動作に関連することが多いですが、スポーツ以外にも手や腕を頻繁に使う職業や日常動作が原因で発症することがあります。
上腕骨内側上顆炎の症状
手や腕を使う動作をすると、肘の内側の痛みが出ることが特徴です。
タオルを絞る、ドアノブを回す動作で痛みを感じるなどが特徴的な症状です。
上腕骨内側上顆炎の原因
手首や指を頻繁に曲げる動作の繰り返しが発症の原因となります。
手首や指を曲げる筋肉(屈筋群)のくっつく部分(付着部)が炎症を起こすことで痛みが出ます。
ゴルフをはじめとしたスポーツやパソコン作業、料理、工具の使用、重いものを持つ作業なども発症の原因となります。
加齢に伴う腱の変性により発症するとも考えられております。
上腕骨内側上顆炎の診断
手をよく使われる方が肘の内側を痛がっているときは疑います。
その上で肘の内側(上腕骨内側上顆)に圧痛があることを確認します。
患者さんに手首を手のひら側に曲げてもらい、医師が患者さんが曲げる方向と反対側に力を加えた時に肘の内側に痛みが出ることもあります。
レントゲン検査も撮影しますが、異常所見が出ることはまれです。
必要に応じて、エコー(超音波)検査やMRIで屈筋群の炎症所見を確認したりすることもあります。
上腕骨内側上顆炎の治療
まずは保存療法(手術をしない治療)を行います。
手の使いすぎを避けるように指導します。
その上で、前腕のストレッチやリハビリを行います。
当院では、疼痛部位に熱と振動の力で治療する超音波治療器を行うこともあります。
痛みや炎症を抑える目的で、内服処方や湿布の処方を行います。
改善がない場合や疼痛が強い場合は、局所麻酔薬とステロイドを混ぜた注射を打つことがありますが、注射の打ち過ぎは逆に腱の自己修復作用を落とすと言われますので、打ち過ぎには注意が必要です。
保存療法で改善しない場合、手術で炎症を起こした腱を処置することもありますが、まれです。
上腕骨内側上顆炎に対する新しい治療法
上腕骨内側上顆炎に対する新しい治療法として、集束型体外衝撃波治療があります。
皮膚の外から衝撃波を照射することで、痛みを取り、組織を修復する新しい治療法です。
ほとんどの上腕骨内側上顆炎に適応となりますが、特に内服・湿布、リハビリ、超音波治療器などの物理療法を行っても改善しない方には良い適応となります。
ステロイドの注射を継続的に打っている方や最近ステロイドの注射を打ったという方は適応にならない可能性がありますので、ご注意ください。
集束型体外衝撃波治療に関しては、診療案内の「集束型体外衝撃波」の項目をご覧ください。
肘内障
肘内障とは
肘内障(ちゅうないしょう)は、小さなお子さん、特に1歳〜5歳くらいの年齢でよく見られる肘の脱臼の一種です。
正確には、肘の関節が完全には外れていない状態ですが、関節の一部がずれてしまって痛みや動かしにくさが生じます。
まだ関節が柔らかくて不安定なお子さんに多く見られるため、育児中の保護者の方にはぜひ知っておいていただきたい疾患です。

肘内障の症状
肘内障になると、お子さんは急に腕を使わなくなり、だらんと下げたままの状態になります。
手を動かそうとすると痛がって泣いてしまうこともありますが、見た目に大きな腫れや変形がないため、外からはほぼ分かりません。
肘ではなく手首や肩を押さえるような仕草を見せることがあり、関節を動かそうとしなくなります。
肘内障の原因
もっとも多い原因は、手を引っ張ったときに起こります。
たとえば、歩いているお子さんがつまずきそうになったときにとっさに手を引っ張ったり、急に走り出そうとしたお子さんを止めようとしたときなどに起こりやすいです。
また、遊んでいる最中に引っ張られる、寝返りの際に腕にねじれが加わるなど、日常のちょっとした動作でも起きることがあります。
引っ張られた際に、肘の靱帯(輪状靱帯)から肘の外側の骨(橈骨頭)がはずれかかった状態になってしまいます。
肘内障の診断
診察では、まず症状や発生時の状況を詳しく伺い、関節の動きを確認します。
通常、レントゲンは必要ありませんが、骨折など他のケガとの見分けが必要な場合は撮影することもあります。
触診と症状の経過から総合的に判断し、肘内障と診断します。
肘内障の治療
治療は、ずれてしまった関節を正しい位置に戻す「整復(せいふく)」を行います。
通常は簡単な操作でほんの一瞬で終わり、元に戻るとすぐに腕を動かせるようになります。
一度肘内障になると再発しやすくなるため、再発予防のために手を強く引っ張らないよう注意が必要です。
文責 上田 英範
(日本整形外科学会整形外科専門医)

